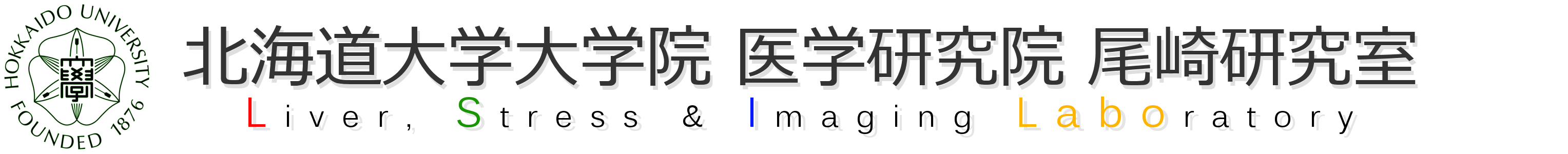研究室(E407)に、ATTO社製 AB-2550 クロノスDio が1台追加されました。2台の装置を連動させたため、16検体の同時測定が可能になりました。(一番奥に見えるのは、BioZeroです。これらを使って、発光・蛍光を使ったさまざまな実験が出来るようになりました。) 
カテゴリー: 生体応答制御医学分野
愛知医科大学・分子標的医薬寄附講座 梅澤一夫教授にご講演いただきました。(2017.12.21)
国立病院機構 福山医療センター 岩垣博巳 院長に講演していただきました。(2017.12.11)
ConBio2017(神戸)に参加しました。(2017.12.13-15)
今年は生化学会と分子生物学会が合同で行われる年で、ConBio2017として、神戸で開催されました。研究室からは、芳賀早苗先生と浅野真未先生が発表しました(12月13日と14日)。また、検査の山口先生・松尾先生との共同研究の発表もありました(12月15日)。演題は以下の通りです。(来年は、別々の開催で、9月と12月のようです。)
肝細胞におけるレドックス依存性ネクロプトーシスの動態解析
芳賀 早苗、菅野 憲、小澤 岳昌、森田 直樹、浅野 真未、伊 敏、尾崎 倫孝
ビルベリー抽出物の糖尿病性網膜症発症・進行予防効果に関する基礎的研究
浅野 真未、芳賀 早苗、柴崎 彩、黒澤 和也、荘厳 哲哉、尾崎 倫孝
カスパーゼ3プローブ発現細胞を用いたクラミジア感染宿主細胞内のアポトーシス制御機構の探索
松尾 淳司、芳賀 早苗、大久保 寅彦、中村 眞二、小澤 岳昌、尾崎 倫孝、山口 博之
光による分子機能制御の研究成果が、Oncology Research誌にacceptされました(2017-8-26)。
“photo-activatable probe for Akt activation”
光照射により細胞の生存のキーとなる分子Aktを非侵襲的・継続的に活性化するツールに関する研究成果を報告しました(Oncology Research誌)。東大・小澤研究室との共同研究です。光感受性物質を応用して細胞内プローブAkt分子を活性化し、それが内因性Aktおよびその下流のシグナルを活性化することを示しました。さらに、それにより細胞が様々なストレスに対して耐性を示すことも証明しました。このプローブは、Aktが関係する様々な細胞現象を研究するための便利なツールになると考えられます。
Sanae Haga, Takeaki Ozawa, Naoki Morita, Mami Asano, Shigeki Jin, Yimin and Michitaka Ozaki, A photo-activatable Akt probe – A new tool to study Akt-dependent physio-pathology of cancer cells -. Oncology Research (in press) IF: 3.957


肝傷害の病態におけるregulated necrosisの関与に関する研究成果を報告しました (2017. 7.15)。
様々な肝傷害における、regulated necrosis (necroptosis)の関わりとそのメカニズムを解析し、論文報告しました。解析は、RIP1およびRIP3蛋白質の相互作用を可視化する光プローブをもちいて行いましたが、apoptosisに対する光プローブも併用することで、necroptosisとapoptosisの関係も明らかとしました。さらに、ligand刺激によるものだけでなく、レドックスにより制御されるnecroptosisの機序に関しても報告しました。
Sanae Haga, Akira Kanno, Takeaki Ozawa, Naoki Morita, Mami Asano and Michitaka Ozaki. Detection of necroptosis in ligand-mediated and hypoxia-induced injury of hepatocytes using a novel optic probe detecting receptor-interacting protein (RIP)1/RIP3 binding. Oncology Research (in press) IF: 3.957