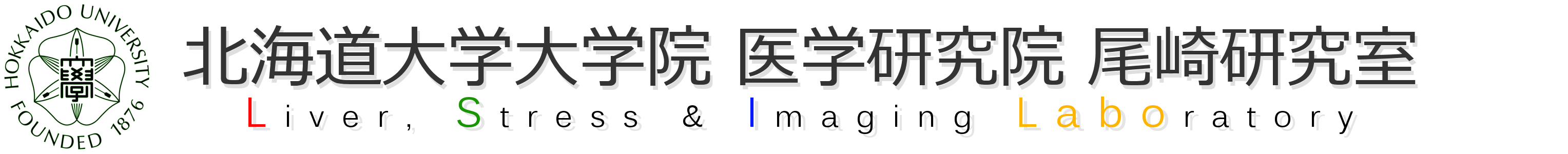生体内でのダイナミックな病態変化を解析する目的で、光を利用した生体イメージングを行なっています。病変の質的診断は、外科診断・治療において手術療法、化学療法の適応、選択、方法を考える上で非常に重要であるにもかかわらず、生体内におけるそれら臓器の状態、病変の特性を直接明らかにする試みはその端緒についたばかりです。そのための新しい解析手法として、蛍光・発光を利用した新たな分子プローブを開発し、細胞・組織環境あるいは分子機能を可視化することが出来れば、生体へのストレス、応答性を理解すること、あるいは同一個体において非侵襲的かつ継続的に生体の機能(状態)をモニタリングすることが可能となります。
生体内でのダイナミックな病態変化を解析する目的で、光を利用した生体イメージングを行なっています。病変の質的診断は、外科診断・治療において手術療法、化学療法の適応、選択、方法を考える上で非常に重要であるにもかかわらず、生体内におけるそれら臓器の状態、病変の特性を直接明らかにする試みはその端緒についたばかりです。そのための新しい解析手法として、蛍光・発光を利用した新たな分子プローブを開発し、細胞・組織環境あるいは分子機能を可視化することが出来れば、生体へのストレス、応答性を理解すること、あるいは同一個体において非侵襲的かつ継続的に生体の機能(状態)をモニタリングすることが可能となります。
A 分子機能・細胞内状態のイメージング
レドックス感受性プローブ、Caspase-3に対するプローブ、小胞体ストレス、Akt機能プローブ、ストレス誘導性蛋白プローブ等を開発し、生体イメージングへの応用を行なっています。これら光プローブは、生体において種々のストレスによる臓器への影響を同一個体にて経時的に理解することを可能とします。これまで、特に生体内酸化ストレスと細胞死の動的解析を行なってきました。

- 肝臓の手術(肝切除および肝移植)において遭遇する「肝臓の虚血・再灌流」あるいは「肝切除」における酸化ストレスを評価する目的で、レドックス感受性を持つGFPを利用した生体イメージングを試みています。臨床における肝臓切除および臓器移植では、一時的な虚血とそれに引き続く血液の再灌流(再酸素化)が不可避ですが、それに伴った重要なストレスのひとつが酸化ストレスです。このストレスを生体レベルで非侵襲的・経時的に可視化出来れば、切除後・移植後の臓器の酸化・還元状態をリアルタイムに把握できます。アデノウィルスベクターにて、マウス肝に特異的に遺伝子導入し、肝虚血・再灌流モデルを作製し、虚血前・中および再灌流後の肝のレドックス状態をイメージングし、レドックスの変化とその後の臓器傷害の程度を検討しました。過度の虚血では、再灌流後にも酸化ストレスは起こらずそのまま壊死状態となりましたが、再灌流直後の酸化ストレスは肝の虚血時間に応じて強くなり、術後傷害に関連していました。虚血・再灌流直後の肝レドックス状態がその後に起こる傷害を予測するマーカーとなり得ると考えられました。
- 細胞へのダメージを可視化するための発光プローブ(ホタル・ルシフェラーゼを利用したカスパーゼ-3活性化プローブ)
ルシフェリン/ルシフェラーゼの化学反応による発光に着目して、生体内用のプローブの作成が試みられています。この化学発光では、比較的長い波長(600nm以上)のシグナルを得ることが可能なために、臓器・生体内の機能評価に適していると考えられます。カスパーゼ-3はアポトーシスの発現に非常に重要な役割を果たしており、広く研究がなされています。このカスパーゼ-3の活性化を検出するために、インテイン(DnaE)のN末端側ポリペプチドとルシフェラーゼのN末端を結合、およびインテイン(DnaE)のC末端側ポリペプチドとルシフェラーゼのC末端を結合した”環状ルシフェラーゼ”という新たなプローブの概念で、その間にカスパーゼ-3の基質配列(DEVD)を挟み込んだプローブが開発されました(東京大学・理 小澤研究室)。このプローブは、カスパーゼ-3の基質部位が切断されるとルシフェラーゼが活性化型フォームに戻り、その活性が回復します。このプローブを導入したAML12肝細胞株においてFas経路を刺激すると、カスパーゼ-3が活性化され、同時にアポトーシスも誘導されました。さらに、マウスを用いて70%肝虚血/再灌流モデルにおける活性化カスパーゼ-3の生体イメージングを試みました。肝虚血後、再灌流時に肝のカスパーゼ-3シグナルが経時的に増強していく様子が観察され、虚血時間とともにシグナルは増強し、かつそのピークも遅延しました。
-
細胞内環境測定(細胞内pH)
また、植物由来の蛋白質の光感受性を利用して、生体における細胞内pHの非侵襲的な測定にも成功しています。植物由来の蛋白質LOV2は、青色光照射によりコンフォメーションを変えますが、この蛋白質にsplitしたluciferaseを結合させると(C-terminal/N-terminal luciferase)、光を照射した際に発光します。光の照射をやめると元通りに発光しなくなります。興味深いことに、光照射をやめてもとの状態に戻るまでの時間recovery timeは、光プローブの発現量、基質量、ATP量などに依存せず、pH値に比例することが分かりました。この性質を利用して、私達はマウス後肢の筋肉細胞が虚血・再灌流を起した際のpHの変化を連続的かつ非侵襲的に観察することに成功しました(PNAS, 2013)。
B 近赤外光によるプローブとプローブ搭載抗体
luciferaseによる発光反応とインドシアングリーンによる蛍光特性を組み合わせて応用したもので、UV照射を必要とせず基質投与により長波長の光(近赤外領域)を発します。これにより、これまで困難であった生体内の比較的深部のイメージングが可能となりました(PNAS 2009, Luminescence 2012)。この光プローブをもちいてマウス実験を行いましたが、図のとおり生体では非特異的シグナルが生じてしまい、臨床応用に対する高いハードルがあることも分かりました。


そこで、私達は「抗原との結合時にのみ活性化する光プローブ」の作製を開始しています(後述)。これに成功すれば、生体イメージングにおける非特異的シグナルを低減できるのみならず、生体内細胞内分子をも標的とすることができると期待しています。
C シグナルにより制御された細胞死(regulated cell death)のイメージングと病態解析
私達は様々な種類の細胞死に対する光プローブの作製を試みており、主として肝臓(肝細胞)の病態を解析しています。特に、シグナルにより制御された細胞死の病態生理学的な役割を中心に解析しています。
Apoptosisは以前から知られているプログラム細胞死のひとつですが、近年になり様々な細胞死が報告されるようになりました。Necroptosis、Pyroptosis、Ferroptosis、Autophagy-associated cell deathなどが良く知られたものです。私達は、それらに対する光プローブを作製し、それぞれの細胞死の臓器機能維持(ホメオスターシス維持)において積極的な役割を果たしているのではないかと考え、研究を進めています。とくに、Apoptosisのバックアップ機構としても働いていることが知られているNecroptosisの病態生理学的な役割と細胞内レドックスの関係、Pyroptosisと肝炎・肝傷害との関係などを中心に検討しています。細胞死の面から、臓器機能のホメオスターシス維持機構、各種疾患への移行病態過程等を理解していければと考えています。
D 細胞内外特異的抗原の生体レベルでの検出
癌を含めた種々の疾患にて、より確実で安全な診断・治療を行なうためには、病変(腫瘍)内の生物学的特性を決定するキーとなる分子を生体外から適切に評価することが有用です。私たちは、東京大学・理・小澤研究室、北海道大学・薬・原島研究室と共同で、光プローブを搭載した抗体をもちいて細胞内・細胞外分子を生体イメージングすることを試みています。
- 抗原分子に特異的なシグナルを担保するための技術開発(抗原抗体結合時にのみ活性化される光プローブの開発):このプローブの開発が成功すれば、「生体」において細胞内・外の分子をターゲットとすることが出来るのみならず、これまで光イメージングの課題であった非特異的シグナルの軽減にもつながります(前述)。
- 細胞内あるいは生体内組織への光プローブ送達に関しての研究:リポソームをベースとしたキャリアシステムにペプチド修飾などを加えることによって、目的となる分子の細胞内への取り込み、細胞質内への放出等をコントロールしています。私たちのシステムでは、従来商品化されたキャリアよりも、素早く効率的に細胞内に送達できることが分かっています。


光・波をもちいた治療のための研究
科学の進歩、医療技術の向上、新薬の開発、術後のQOLに対する意識の変化などの様々な理由により、今後はより低侵襲で、より的確な治療(必要にして十分な治療)が望まれています。切除を中心とした外科治療分野においても、近年低侵襲の治療法の開発が進んでいますが、私達はそれをさらに推し進め、開胸、開心、開腹などにおける直視下の手術あるいは内視鏡下の手術において、新しい外科治療法を生み出すためには革新的なインフラ技術の開発が必要と考えています。
近年、“光”を用いた様々な技術開発が進められています。オワンクラゲ由来の蛍光物質であるGFPを発見した下村修博士は、その功績に対し2008年ノーベル化学賞が贈られましたが、それ以降、光を用いた技術の研究には目を見張るものがあります。蛍光物質であるICG(インドシアングリーン)は、以前から肝機能を評価するものとして用いられてきましたが、最近では腫瘍のリンパ節転移の術中診断に用いられるようになりました。私達は、以前から光イメージングによる診断・治療の研究を進めており、特にルシフェラーゼ等をもちいた生物発光によるイメージング技術の医療への応用を目指しています。
a) 光感受性蛋白質による細胞治療(PA-Akt: photo-acitvatable Akt)
Akt(PKB)は、細胞が生存していくために欠かせない分子のひとつです。この分子の活性を制御することが出来れば、細胞の生存能をコントロールすることが可能と考えられます。私達が共同研究を行っている東大・小澤研究室では、植物細胞のもつ光感受性蛋白質を利用して、このAkt分子の活性を制御することに成功しています(Sci Rep. 2015)。私達は、この手法により、様々な種類のストレス(飢餓、低酸素など)に対して細胞に耐性をあたえることを確認しています。こういった技術が確立すれば、創傷の治癒促進、細胞・組織・臓器などの移植医療、再生医療に貢献できるかもしれません。

b) 波による物理的特性の変化を利用した細胞治療を目指した研究
“光”はレントゲン線と違い組織透過度、解像度等は低いものの、外科手術への応用にあたり、次のようなアドバンテージがあります。①測定装置が小型・安価で手術場にも手軽に持ち込める点、②蛋白質・遺伝子に由来する生物学的情報を得るためのプローブ作製が可能である点(テーラーメイドで作製可能である)、③いくつもの生物学的情報を同時に得ることが可能な点、などです。
また、医療において“波”を用いた技術は既に様々な分野で利用されています。波は光よりも組織透過性が優れているため、超音波エコー装置では、深部組織の解剖学的情報を詳細に知ることが出来ます。探触子自体も小型で済むため、日常医療あるいは手術中の診断にも応用可能です。ラジオ波では、発生する“熱”を利用することで肝腫瘍等の熱凝固治療も行われています。最近になり、このような物理的ツールが、上述の分子レベルでの診断・治療に貢献する可能性を示す基礎的な研究成果が報告されるようになってきました。
このような状況下で、私達は、“光”と“波”の特性を利用し病変組織・腫瘍細胞内の分子情報をリアルタイムに知り、低侵襲で理論に基づいた新たな外科治療を行うための基盤的研究を行おうとしています。ナノレベルの技術に基づいて革新的な術中診断・治療技術を開発することにより「これまでにない外科分子診断・治療学の創成」を目指しています。